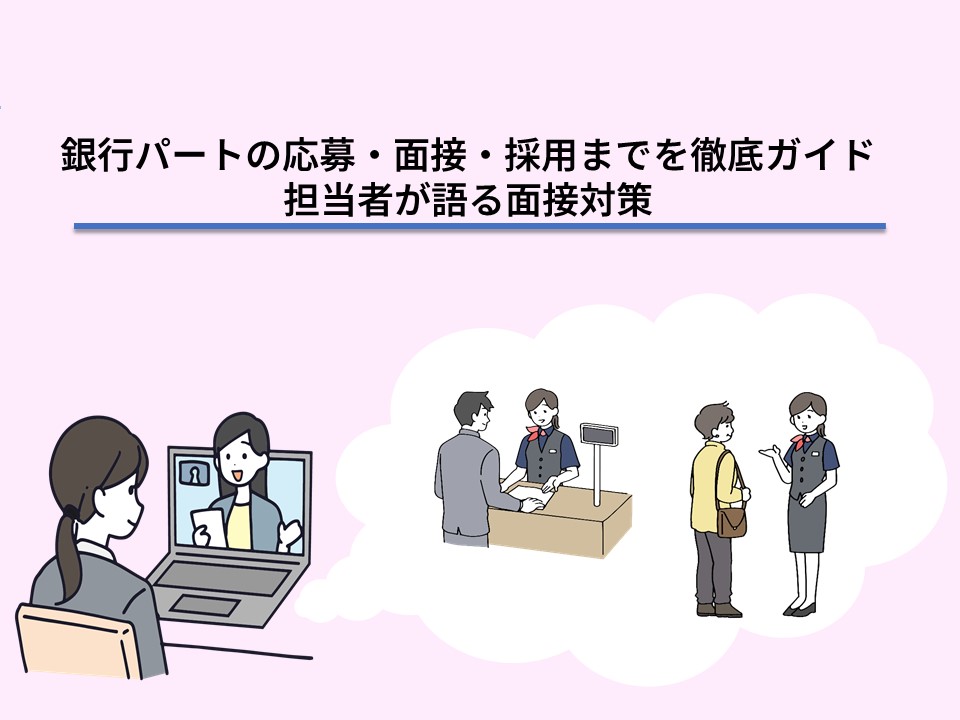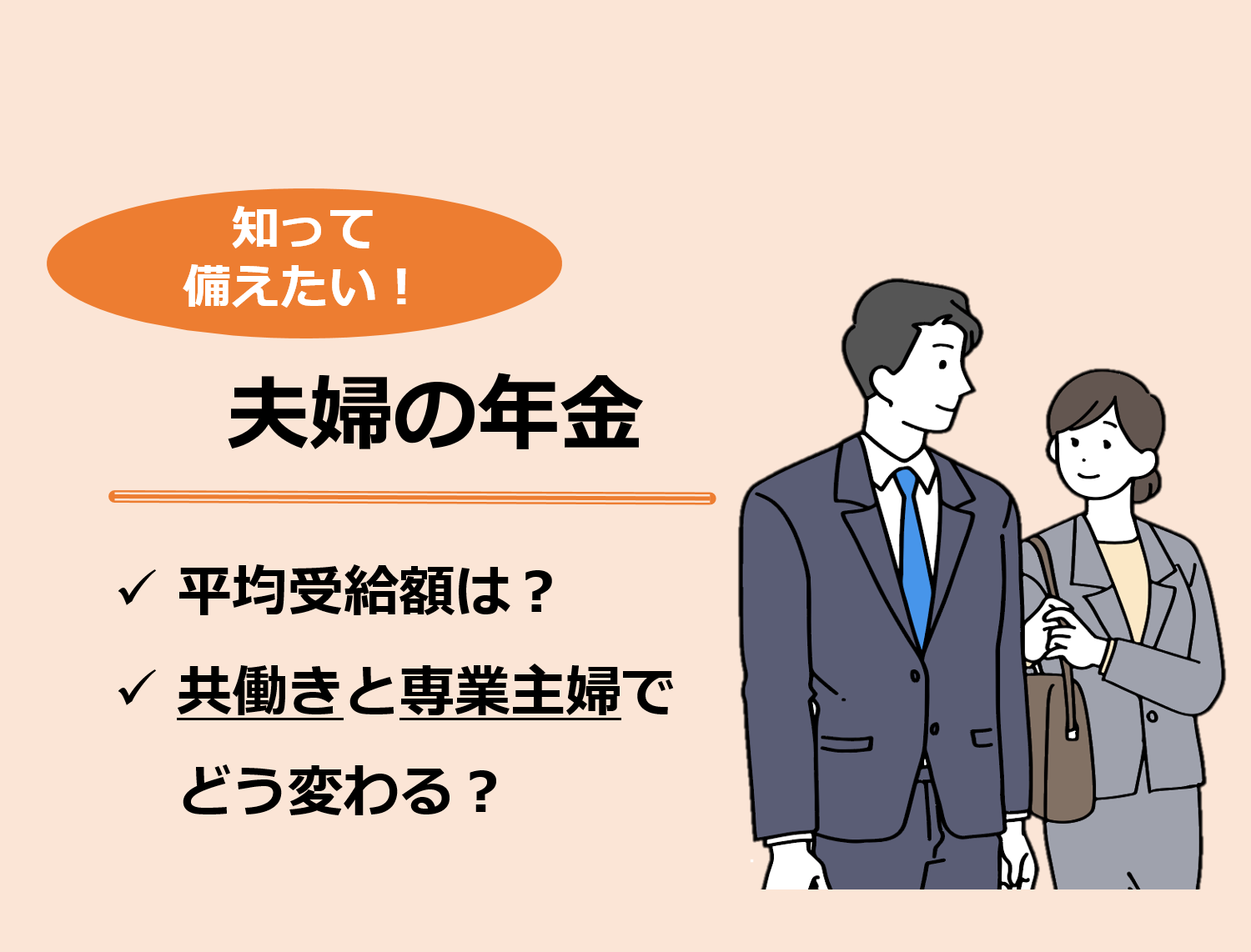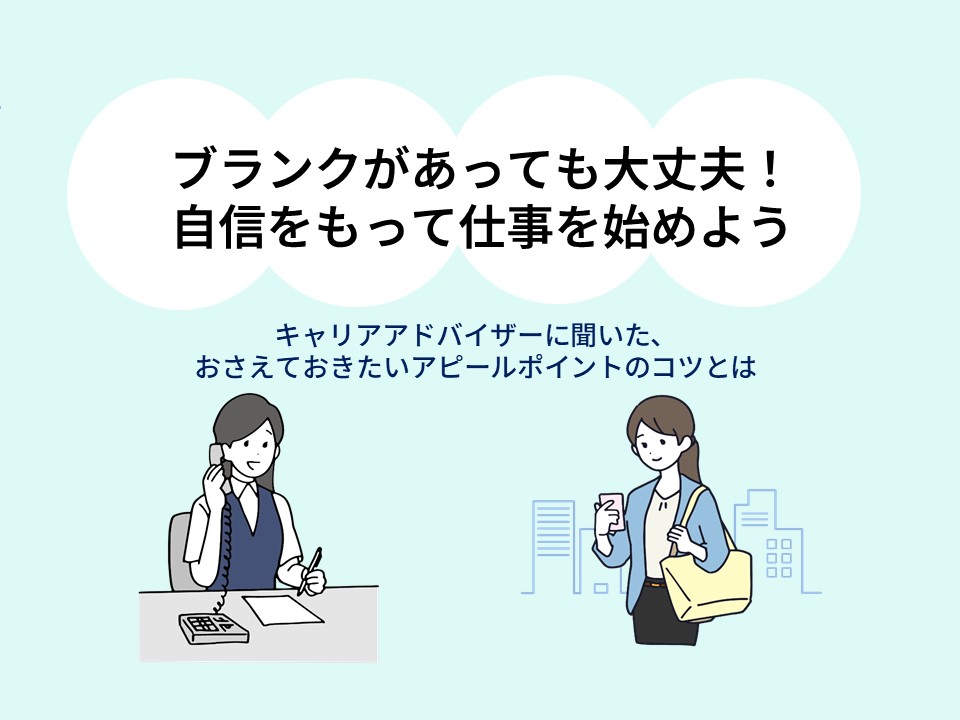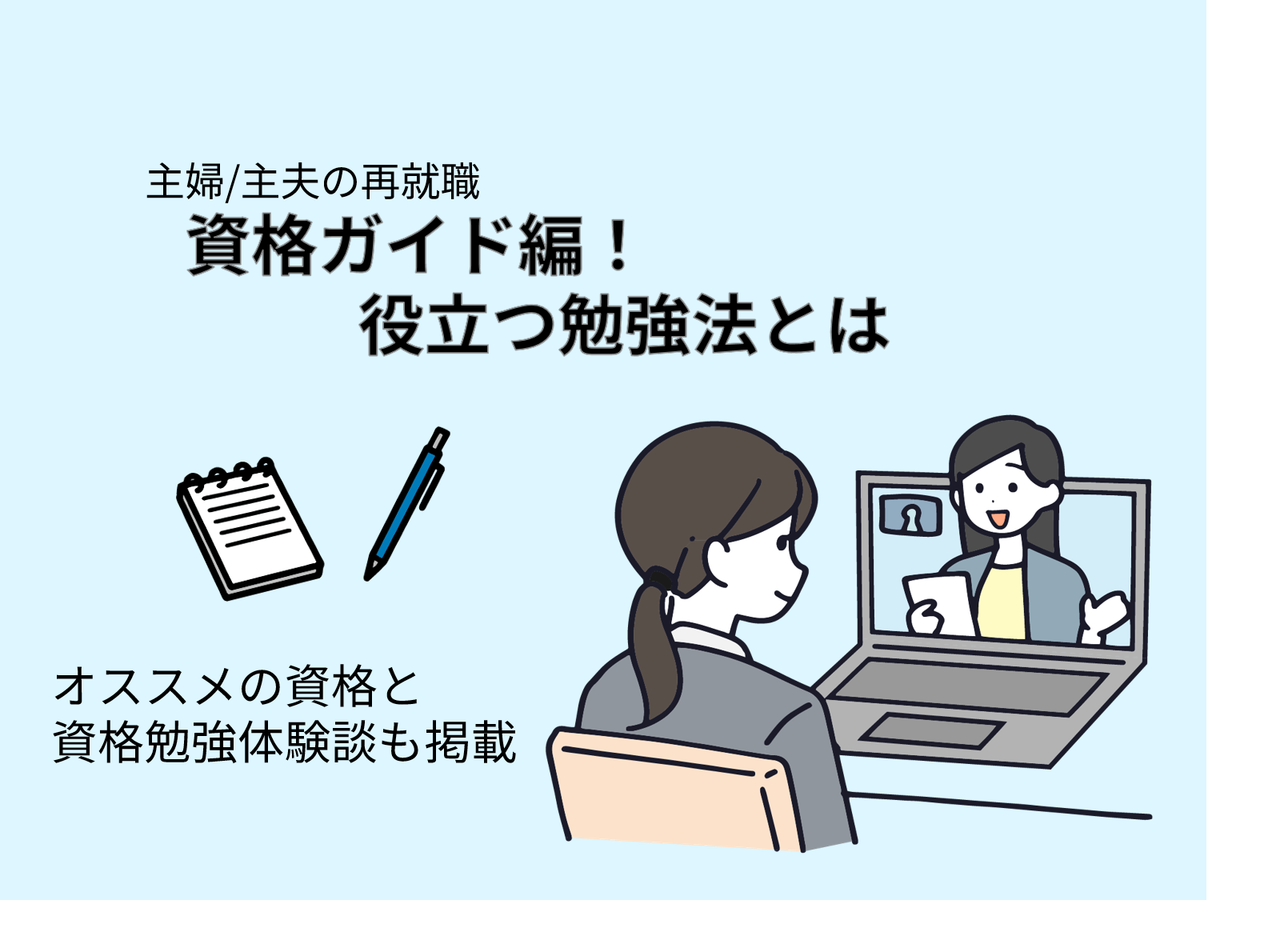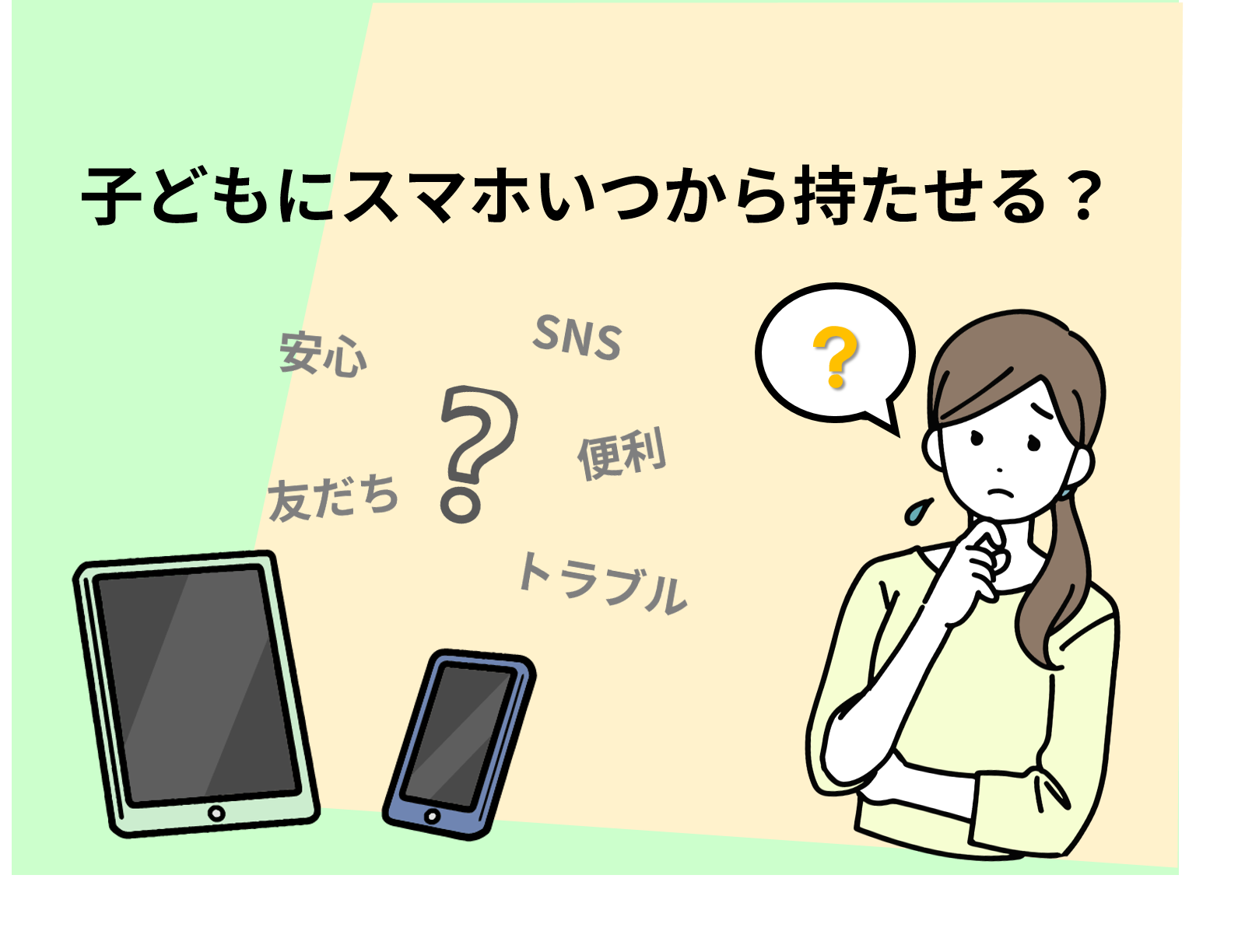【働くママ必見!】朝の家事動線&ルーティンで時短する方法
復職や再就職を考えているけれど、今の家事育児の時間配分がどうなるか想像できない…と不安に思っている方もいるのではないでしょうか。今は不安な気持ちを抱えていても、少しずつ準備を整えていくことで、自然に心と時間にゆとりができるもの。時間のない朝を有意義に使うために、朝の家事動線について事前準備の工夫や考え方をご紹介します。準備|家事の区分けをする朝の家事ルーティンを考えるうえで、「どの家事をいつやるか」といった視点を持つのは大切です。最初に、主な家事をリストアップしてみましょう。手順1|家事を「毎日やりたいもの」と「そうでないもの」にわける準備で書き出した家事は、ご家庭の生活スタイルによって優先順位が変わってきます。たとえば、以下のように優先する家事が違うケースがあります。子どもがスポーツクラブに入っているため、毎日洗濯したい日中は外出が多いため、掃除は週に2回で十分このように、ご自身や家族にとって必要な家事を見直し、優先度の高い順に並べると良いでしょう。手順2|「毎日やりたいもの」のうち、「朝やりたいもの」と「そうでないもの」にわける毎日やりたい家事の中から、あなたの気になるポイントに合わせて朝やりたいものと、そうでないものに分けてみましょう。太陽の光に当てたいから、朝洗濯物を外に干したい夕方時間がないから、炊飯器をセットしたい増えすぎてしまった場合は、帰宅後や時間の制約が少ない休みの日に回せないか考える必要があります。最低限やりたい事ルーティンと、理想的な家事ルーティンの2パターンを考えて見るのも良いかもしれません。毎日のことなので、無理のないスケジュールを組み立てることがポイントです。手順3|家事の所要時間を把握する手順2で書き出した家事にかかる時間を確認しましょう。実際に測ってみると、思っていた所要時間とずれがあることも。この段階では、測った時間よりも少し余裕を持って捉えると後々調整しやすくなりますよ。最低限の家事ルーティンを行った場合の所要時間と、理想的な家事ルーティンの所要時間を並べてから出発時間を考えると、自ずと起床時間も見えてきますね。家族内共有|担当を決める抜き出した家事と所要時間を家族へ共有し、担当を決めることも一つの選択肢です。朝やりたい理由と所要時間が分かっていると、スムーズに担当決めができることでしょう。決め方の一例をご紹介します。決め方例①|得意分野で分ける各自が得意な家事や、負担を感じにくい作業を担当することで、精神的なストレスを減らすことができます。力作業や細かい作業など、得手不得手を基準に分担するのもひとつの方法です。決め方例②|家を出る時間で分ける片方が在宅勤務で時間の余裕があるから多く負担する、夜勤明けの日はゴミ出しのみ担当するなど、各々の家庭の事情に合わせた無理のない担当を決めていきましょう。子どもの準備|ルーティン化し、自分のことは自分で子どもが小学生になると、乳幼児期と比べて自分でできることが増えてきます。学年が上がる、母親が働きだすなど、環境が変わるタイミングで自分のことを自分できるように、早めにルーティン化すると大いに助かります。自分でやる工夫小さな工夫で子どもが自分でできることは増えていきます。次のような工夫を参考に、ご家庭でも取り入れてみてはいかがでしょうか。可視化する朝やるタスクを時系列にホワイトボードに書いておくなど、子ども自身の目で確認できるようにしましょう。前日に準備をすませる学校の準備や、翌日着る服の準備は前日のうちにしておきましょう。余裕のある時間にやっておくことで、忘れ物の防止にもつながります。朝ごはんに火を使わないシリアルに牛乳を入れるだけ、パンを自分でトースターに入れて焼くなど、本人ができる位置に動線をおくことで、自分でできることが増えます。火を使わないことで、慌ただしくて親の目が届かない時間でも安心です。具体的なスケジュール例と時短ポイントここでは、小学生の子どもを持つ働くママのタイムスケジュールをご紹介します。それぞれのこだわりポイントや工夫ポイントも必見です。Aさんの場合(小学校高学年女児、低学年女児あり)Bさんの場合(夫婦、小学校低学年男児あり)Cさんの場合(夫婦、小学校中学年男児あり)Dさんの場合(夫婦、小学校低学年女児あり)家事育児を時短するコツ家事工程のひとつひとつを見直して、そもそもの家事にかける所要時間や精神的負荷を減らしてみましょう。次にご紹介するような工夫で、取り入れられそうなものを探してみるのはいかがでしょうか。“ながら”作業で効率的に日々の生活の“ながら”で行うことで、重い腰を上げて家事をしなくては、ということがなくなります。また、こまめに掃除等を行うため、汚れがたまらず一石二鳥。小さいことからの積み重ねが大切です。まずは、以下のような作業を取り入れると良いでしょう。最後にお風呂に入った人が浴槽を洗うタオルを洗濯する前に洗面所を拭く皿洗いのついでにシンクを洗う夕飯時に翌日の朝ごはんの分も作る家事の工程を減らす家事のタスクが多い時は、ルーティン化している家事動線を見直してみると良いでしょう。毎日やる家事なら一つの部分を変えるだけで、大きな時短につながります。次のような工夫をしてみるのはいかがでしょうか。ゴミ箱の数を減らす洗濯物は「掛ける収納」にする冷凍食品の野菜を活用する時短家電を活用する時短に欠かせないのが、時短家電の存在です。導入コストはかかりますが、活用できればコストを上回る満足度が得られます。時短家電については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。家事分担成功の秘訣と時短家電紹介!最新データで徹底解説まとめ|トライ&エラーを繰り返し、自分に合ったルーティンを今回は、朝の家事動線について事前準備の工夫や、考え方をご紹介しました。家族構成や環境によって書き出す家事や時短すべきポイントは変わります。想定していた家事動線で思うようにいかなくても大丈夫です。この記事の内容を試しながら、ご自身に合った朝の家事ルーティンを見つけてみてくださいね。みずほでは、働くママを応援しています。こちらの記事も参考にしてみてください。家事分担成功の秘訣と時短家電紹介!最新データで徹底解説