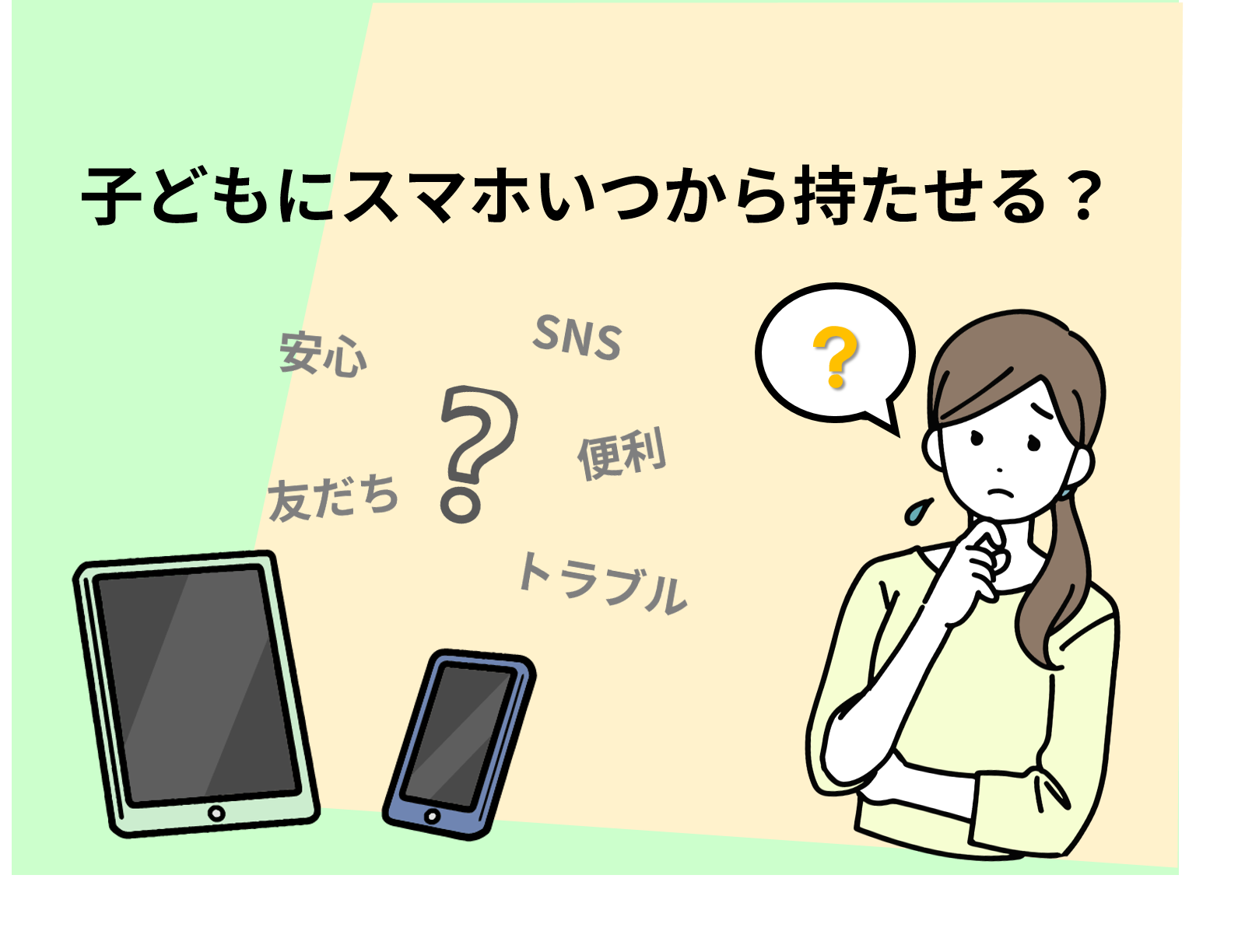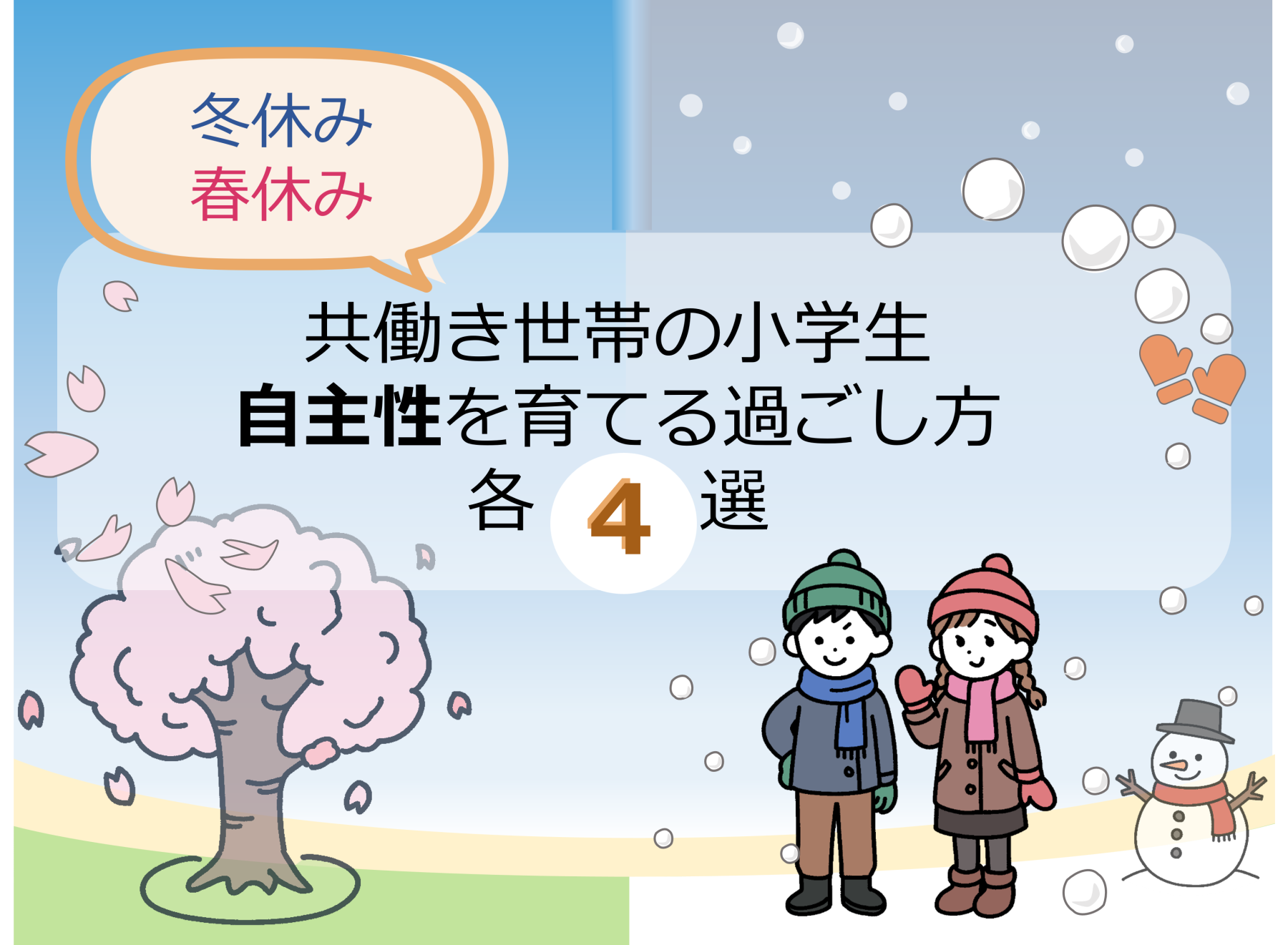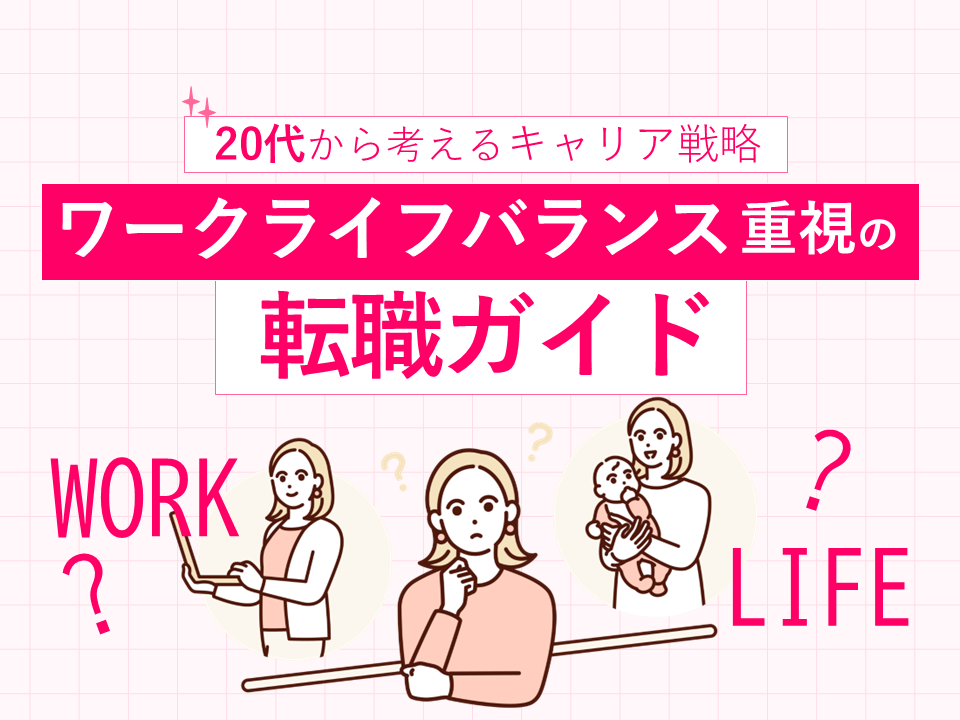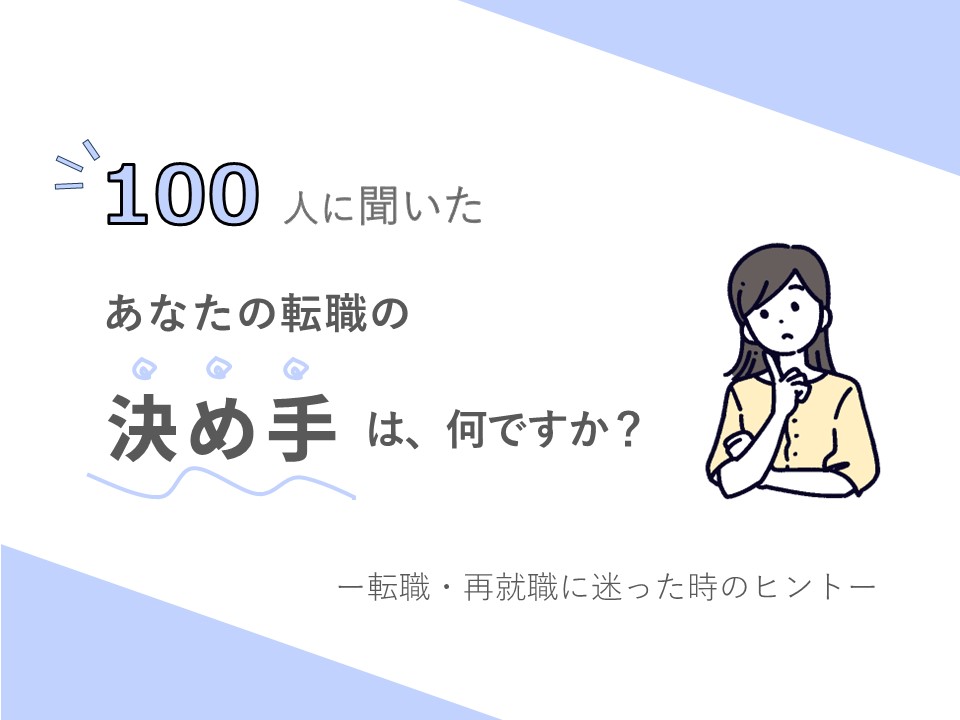《実例つき》小学生にSNSは危険?実際のトラブル内容と保護者の対策
家事と仕事の両立|知る、つながる、働くわたし

あなたは“小学生×SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)=悪影響”というイメージはありませんか?日々のニュースや子どもたちの話からSNSが要因となる事件や身近なトラブルについて見聞きすると思います。
一方で、小学校の授業ではSNSを活用し、ダンスや運動についての動画を見るときがあります。今の子どもたちにとってはSNSやインターネットは生活の一部となっているとも言えるでしょう。
SNSが当たり前のように存在するこの時代、保護者として何ができるのでしょうか。
この記事では、実際に起きたトラブルの内容や先輩ママの声を紹介します。SNSと上手に付き合うための参考にしてください。
目次
小学生がSNSを使うことについて
SNSとは、友だちとメッセージのやり取りや、写真・動画を見せ合えるアプリ・サービスです。SNSは、大人にとっても子どもにとっても生活の一部になっています。
しかし、小学生は心や考え方が成長している途中で、判断力が十分ではありません。そのため、 SNSの利用によって多くのトラブルが発生しています。
次の項では、なぜ小学生のSNS利用が増えているのか解説していきます。
SNSを使う小学生が増えている背景
スマートフォンやタブレット端末が普及し、小学校の授業媒体として1人1台タブレット端末が配布される時代です。
また、固定電話や公衆電話の減少もあり、自分のスマホを持つ小学生が増えています。
親や友だちとの連絡手段として、LINEやYouTube、Instagramが当たり前のように使われており、SNSは子どもの生活に深く根付いているでしょう。
SNSを使うときの注意点
具体的にはどのような危険があり、どのように注意したらよいのでしょうか。SNSを使うときの4つの注意点を、以下にまとめました。
個人情報(プライバシー)が流出してしまう
「ついうっかり」自分や家族の写真、名前や住所、学校名などをSNSに載せてしまう。
個人情報を公開してしまうと悪用される危険性があります。気を付けているつもりであっても、些細な情報から個人が特定されることもあります。投稿する際には十分、注意が必要です。
いじめやトラブルの原因になる
「ちょっと気持ちが大きくなって」いつもより汚い言葉、強い言葉を使ってしまう。
SNS上での言葉のやりとりは誤解を生みやすく、いじめやトラブルに発展することがあります。
表情や声色が分からないトーク画面やオンラインゲーム中に会話をするため、日常よりも表現が強くなっていないか注意が必要です。
時間を使いすぎてしまう
「あともう少しだけ」と思いつつダラダラ時間を過ごしてしまう。
SNSは刺激的でつい夢中になってしまうため、勉強や睡眠時間が削られる可能性があります。
自分で時間の管理をすることが難しい場合は、使用時間を決めるなど注意が必要です。
事件・事故に巻き込まれてしまう
「何度もSNS上で話したから」と簡単に現実の友だちのように錯覚してしまう。
SNS上で知り合った友だちに写真を送ったり、会いに行ったりすることで事件に巻き込まれる可能性があります。
安全なゲームで遊んでいたつもりが、違法なサイトに誘導されていたケースもあるので、注意が必要です。
実際におきている小学生のSNSトラブル
メッセージアプリでのトラブル
- クラスの友だち数人でグループメッセージをしていたが、急にブロックされ仲間はずれにされた
- アプリ上でケンカが始まり、ケンカをしている子、仲裁している子のやり取りでメッセージが止まらなくなった
- 友だちが家族の写真を連投し、他の子にも送るよう強く指示した
オンラインゲームでのトラブル
- 友だちとオンラインゲームで遊んでいたところ、急に外された
- オンラインゲーム中、強い言葉で数人の仲間から責められた
- ゲームのキャラを強くするために、課金して装備を買うよう言われた
その他のトラブル
- 同性の同い年だと思っていたが、年上の異性であった
- 写真を投稿したところ個人を特定されてしまった
- 安全なサイトを見ていたが、誘導されたサイトが悪徳で金銭を要求されてしまった

保護者ができるトラブル防止策
ここまでは、SNSを利用することで起きるトラブルについてみてきました。
大切な子どもがトラブルに巻き込まれるのを防ぐために、私たち親ができることは何でしょうか。
代表的な防止策3つを案内します。
ペアレンタルコントロールを使う
子どもの安全のため保護者がネット利用環境を整えてあげることをペアレンタルコントロールといいます。ペアレンタルコントロールの代表としてフィルタリングがあります。
フィルタリング活用する
フィルタリングとは、利用時間やアプリのインストール、課金アイテムの購入などさまざまな項目を制限できる機能です。
- 子どもにふさわしくないコンテンツ(暴力的、性的、年齢に対して不相応なものなど)へのアクセスを制限する
- 子どもの電子機器の使用時間を管理し、過度な使用を防ぐ
- 課金機能の利用を制限する
- 子どもの閲覧履歴やアプリの使用状況を、保護者が確認できる
- 子どもの位置情報を確認する
※現在法令等により、携帯電話会社とその販売代理店には、18歳未満の青少年が利用する端末の契約時に原則「フィルタリングサービス」を提供する義務が課せられている。
参考:総務省「フィルタリング(有害サイトアクセス制限サービス)をご存じですか?」
家庭内ルールを決める
フィルタリングを活用するとしても、利用時間や制限をかける内容については、各家庭でルールを決めておく必要があるでしょう。
「平日の利用時間は〇時間」「週末の利用時間は△時間」と生活リズムによっても変わってくると思います。
また、制限だけではなく「困ったらすぐに相談する」といった約束をしておくことで、トラブルが起きても早期に対応できます。
先輩ママの声
| 利用中のSNS | LINE、YouTube、オンラインゲームなど |
| 家庭のルール | ・フィルタリング設定済 ・宿題など、やるべきことをやらないときにはスマホを1週間没収する |
| トラブル経験 | 友だちに成りすましてTikTokアカウントを登録していると疑われました。 お友だちの動画がTikTokに公開されたらしく、ケンカ中だった息子がそれを載せたと責められました。 スマホを見せてTikTokアプリをダウンロードしていないことと親の許可がないとダウンロードできない状態であるのを伝え疑いは晴れたようです。 |
| 利用中のSNS | LINE、YouTube、Instagram、TikTokなど |
| 家庭のルール | ・フィルタリング設定済 ・自室での利用は禁止 |
| トラブル経験 | 以前、グループラインで仲間外れにされたことがありました。 そのことがあってか、通知音に振り回されているように見えます。 常にスマホを気にしているので、新たなルールを決めようと思っています。 |
| 利用中のSNS | LINE、YouTube、オンラインゲームなど |
| 家庭のルール | ・フィルタリング設定済 ・LINEのお友達やトーク履歴確認 |
| トラブル経験 | 仲間を集めて戦うオンラインゲーム中に、突然外され戦えなくなったことがあります。 その時に「お前は弱いから入ってくるな」「一緒にやりたかったら装備買ってこい」などと言われたようです。 幸い1人の子からの攻撃だったので、他の子とは問題なく遊んでいます。 |
まとめ
これまで述べてきたようにSNSの利用は、トラブルや注意すべき点がたくさんあります。小学生、特に高学年であっても、まだまだ心も体も成長段階です。実際に会ってコミュニケーションを取るときと比べて、トラブルが多く起きてしまうのは容易に想像できるでしょう。
しかし「SNSは危険だから排除する」のではなく「子どもの成長に役立つツール」と前向きに捉えることもできます。
SNSは離れている人と連絡を取れたり、情報を共有できたりと、とても便利です。また、自分の作品や技術を発信すると表現力が成長し、称賛やアドバイスで刺激を得られるでしょう。このようにSNSは使い方次第で便利で楽しいツールになります。
私たち保護者に必要なことは「トラブルが起きた時にすぐに相談できる存在」でいられるような関係性を作っておくことなのではないでしょうか。
関連記事